近年の人工芝研究
3-1024x756.png)
前回は人工芝の歴史についてお伝えしました。天然芝の農薬による健康被害、養生期間は使用できないといった課題を解決するために生まれた人工芝。しかし、その人工芝は、ケガのリスクや高い表面温度による低温やけど、ゴムチップ緩衝材による健康課題や環境問題などを内包していました。今回はその課題解決に向けた人工芝の最新研究をお伝えできればと思います。世の中がよくなるよう日々、様々な技術が進歩しているように人工芝もより良い環境づくりに貢献するために進歩しています。
環境を整えることができるのは大人だけ
2-841x1024.png)
私は園庭や校庭、スポーツをするグラウンドは芝生化したほうが良いと心から思っています。そして、天然芝と人工芝、どちらのメリットも合わせた芝生があれば良いのにと思っていました。環境のせいで知らず知らずのうちに発育発達が遅れたり、スポーツをする楽しさに気づきにくかったりというのはあってはならないと考えています。子どもたちが環境を選ぶことは容易ではありません。どの選択肢を選んでも子どもたちが健やかに成長できる環境を整えていくことが大人の責務ではないでしょうか。
最新の人工芝研究

今回は現在明らかになっている最新の人工芝研究をご紹介したいと思います。最新の研究は、充填剤であるゴムチップの有害性と環境に与える問題についての研究やその緩衝性の評価についての研究が盛んに行われています。例えば、充填剤が自然環境へ流出しないように様々な実験をした研究があります。この研究では競技場の排水溝にトラップを装着したり、競技場の水路の中にくぼみをつくることで充填剤を沈降させて捕獲したりする方法の有用性を示した研究です。また、充填剤、特にゴムチップが自然界へ流出したらどうなるのかを明らかにした研究では、ニジマスが間違って食べてしまい、生態系に悪影響を与える可能性を示唆しました。緩衝性の評価については、ランニング中にどのような衝撃が起こるのかのモデル化、より人の行動に近い緩衝実験機器の作成を目指した研究があります。
これからの人工芝

最新の研究は素晴らしい発見ばかりですが、現場に降りてくるまでまだまだ時間がかかりそうです。それでも現場はどんどん進み、近年では充填剤不使用の「ノンフィル人工芝」というのが開発されています。ノンフィル人工芝も各種メーカーが工夫を凝らし、様々なタイプが生まれています。ノンフィル人工芝についての研究はまだまだ発展途上ですが、実際にノンフィル人工芝を使用している声を聴くと天然芝と人工芝の良い面だけを兼ね備えていることは間違いないと思います。これから私はノンフィル人工芝についての研究に励み、子どもたちやスポーツ選手によりよい環境を届けられるような環境づくりに貢献したいです。
これまでは芝生化についての歴史をお話ししました。次回からは、芝生からもう少し掘り下げて「緑化」が与える影響についての研究をご紹介したいと思います。
大城 卓也(おおしろ たくや)
1992年4月13日沖縄県出身。聖カタリナ大学准教授(健康スポーツ学科)。
8歳で野球を始め沖縄尚学高校、順天堂大学へ進学。大学では保健体育教員免許を取得。硬式野球部に所属し4年次に監督としてリーグ優勝。大学院ではスポーツ組織・マネジメントの領域から人工芝の抱える課題に着目。
2018年聖カタリナ大学に着任しスポーツビジネスやマーケティングの講義を担当。硬式野球部の創部に携わり、1年で四国地区1部リーグ昇格に貢献。オールスター戦コーチにも選出。現在、地域の高校野球部での指導や研究活動を通じ、地域還元に尽力している。
参考文献
小林、竹政ら(2024):「人工芝競技場由来のマイクロプラスチックの自然環境への流出防止装置の作製」,Journal of Kanagawa Sport and Health Science, 57(1),pp17-36.
小林、千葉ら (2023):「ニジマスによる人工芝競技場のゴムチップの摂取」, Journal of Kanagawa Sport and Health Science, 56(1), 13-25.
湯川、松崎ら(2018):「ランニング着地衝撃を考慮したロングパイル人工芝の緩衝性評価」 In シンポジウム: スポーツ・アンド・ヒューマン・ダイナミクス講演論文集,2018 (pp. D-18),一般社団法人日本機械学会.
湯川、腰ら(2021):「スパイクスタッドを用いたロングパイル人工芝の2方向動的緩衝性評価」,In シンポジウム: スポーツ・アンド・ヒューマン・ダイナミクス講演論文集,(pp. C-6),一般社団法人日本機械学会.





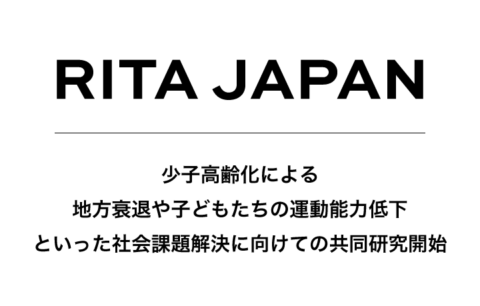




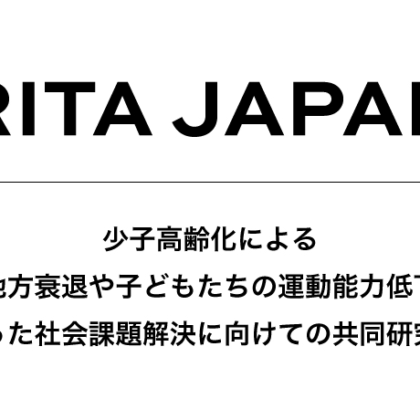







コメント